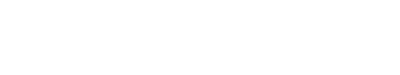『広告批評』袋とじの衝撃【新保信長】新連載「体験的雑誌クロニクル」5冊目
新保信長「体験的雑誌クロニクル」5冊目
1986年のチェルノブイリ原発事故を受けて、日本の原発広告を検証する「明るい明日は原発から」(1987年6月号)も見どころたっぷり。〈この子たちの未来のために。〉〈いまや、原子力発電もクルマ、カメラなどと並んで世界に誇れる技術です。〉〈このスイカも3分の1は原子力で冷やしたんだね〉といったキャッチコピーは当時から胡散臭さ満点だったが、現実に福島原発事故が起こった今見るとさらに白々しい。

宮崎勤事件でオタクバッシングが起きたときには、「がんばれ、おたく」(1989年11月号)という特集を組んだ。登場するのは、糸井重里、橋本治、岸田秀、森山塔、黒川創、岡崎京子、中森明夫、野々村文宏、浅田彰、いがらしみきお、市川準、稲増龍夫、えのきどいちろう、川本三郎、渋谷陽一、萩尾望都、村上知彦といった錚々たるメンツ。昭和から平成への変わり目を31人の文化人へのアンケートで活写した「CMが消えた二日間」(1989年2月号)と同じく、時代の記録としても貴重だろう。
もちろん、そうした時事ネタのみならず広告そのものの特集もあって、1984年10月号では「サントリーのここが嫌いだ!」とぶち上げた。田中裕子の「タコが言うのよ」(樹氷)、ランボーやガウディをイメージした贅沢な絵作り(ローヤル)、松田聖子の歌とペンギンのアニメ(缶ビール)など、当時の広告界で燦然と光り輝いていたサントリーにあえてケンカを売るスタイル。「おすぎとピーコのCM悪口大会 サントリー編」なんて記事もあるが、この号にもサントリーは素材を提供しているわけで、企業側にもこういうものを受け入れる余裕があったのだ。というか、結局この特集自体がサントリーの宣伝になっている。批評は、たとえ辛口だったとしても、単なる悪口とは違うのだ。
連載「アド・トレンド」では、最新の広告を解説・批評する。毎年12月号は「広告ベストテン」企画を実施していた。広告が時代と文化の最先端にいた80年代、その広告を批評する雑誌もまた、時代と文化の先端を走っていたのである。
そもそも誌面に登場する広告制作者、とりわけコピーライターがカリスマ的人気を誇った時代でもあった。前出〈とにかく死ぬのヤだもんね。〉のコピーを書いた糸井重里が、その筆頭。今の糸井重里はツイッター(自称X)で“ズレたこと言う痛いおじさん”みたいになっているが、当時は〈不思議、大好き。〉〈おいしい生活〉などのコピーで脚光を浴びていた。1982年9月号では「糸井重里全仕事」なる特集が組まれるほど。それが売れたらしく、のちに別冊『糸井重里全仕事』も刊行された。同様に当時の人気クリエイターの別冊『仲畑貴志全仕事』『川崎徹全仕事』『土屋耕一全仕事』も出た。
糸井重里が残念な感じになり、電通や博報堂などの広告代理店が中抜きマシンでしかないことが明らかになった今となっては恥ずかしい限りだが、当時の私はコピーライターという職業に憧れていた。その話は別項であらためて書くけれど、『広告批評』が自分の雑誌遍歴のなかで重要なポジションを占めていることは間違いない。
90年代に入っても、『広告批評』は広告というフィルターを通して社会を見続けた。「広告戦争イラクVSアメリカ」(1990年10月号)、「『生活大国』って、ナンですか?」(1993年1月号)、「『ヘアヌード』シンドローム」(1994年10月号)など、時宜を得た特集を組む。「村上春樹への18の質問」(1993年2月号)、「細川護熙の広告的研究」(1994年2月号)、「それは手塚治虫から始まった」(1996年2月号)など、一人の人物にスポットを当てた特集もあった。